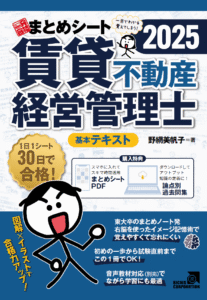今日は、令和2年度 第48問について解説します。
建築基準法の天井高規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 居室の天井高は、2.1m以上としなければならない。
② 一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要である。
③ 天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定される。
④ 一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、居室として使用することはできない。
解説
建築基準法の規定に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
居室の天井高は、2.1m以上としなければならない。
〇適切です。
居室の天井は、床面からの高さが2.1m以上でなければなりません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要である。
〇適切です。
同じ室内で天井の高さが異なる部分や、傾斜天井がある場合には、平均して2.1m以上の天井高が必要とされています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定される。
×不適切です
天井高が 1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の1/2未満であるなど、一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、床面積には算入されず、建物の階数としてもカウントされません。
つまり、天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一未満であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定されません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、居室として使用することはできない。
〇適切です。
ロフトはあくまでも物置としての扱いであり、居室として利用することはできません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。